佐原シリーズで何度か触れているが、佐原は醤油や酒の醸造が盛んであった街である。穀物をそのまま江戸へ送るよりも、醸造して付加価値を付けて送った方が儲かったという事のようである。

江戸時代には四十数軒の造り酒屋があったとの事であるが、現在では東薫酒造と馬場酒造の2軒が残るのみとなっている。ともに直売店が設けられ直販で酒を購入する事ができるし、見学をすることができる。
小生が見学をお願いしたのは、東薫酒造であった。御存知の方も多いと思うが日本酒の醸造は寒仕込みと言って、冬に仕込みを行う醸造法が一般的である。小生が訪れたのは9月だったので、見学の対象となったのは発酵を行う酒樽や醪を絞る、施設の見学を行う事となった。
酒蔵を見学するのは初めての経験ではないが、こういった経験は何回経験しても、なかなか楽しいものである。見学後は直売店で酒を購入する事になったのは言うまでもない。

酒蔵の建物は意外と小さめです

造り酒屋には必ずある杉玉です。

現在使われている酒樽は木製ではありません。表面は鋼鉄、中はホーローでできているそうです。

昭和42年に造られた樽のようです。
![_digital_images_2011_09_28_imgp0102[1]](https://seiryuh.org/wp/wp-content/themes/simplicity2/images/1x1.trans.gif)
少々写真は暗いですが酒樽の上です。こちらから醪を撹拌します

こちらは安い酒で使用される醪の絞り機。油圧で絞っておきます。

高いお酒はこちらで絞るそうです。基本的には醪の自重で絞っていきます

東薫酒造の看板銘柄の「叶」の大吟醸。写真の300mlで1,500円ほど

もう一つ買い求めたのが、どぶろく。5合瓶で1,100円でした。

グラスに注ぐとこんな風に良い発酵加減です
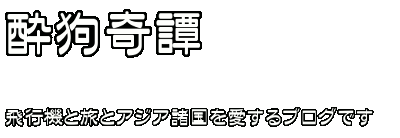


できたてのお酒はおいしいんでしょうね
アルコールのぴリリ感が少なくて・・・
このあたりの土地は
酒やしょうゆなどの麹産業が盛んだと言うことは
そういうなんというか麹菌が土に多く含まれた土壌なのでしょうか
以前造り酒屋のお客さんがありまして。
酒を造っている過程を結構見せてもらいました。
酒樽は発酵している最中に上から覗き込んでいると酸欠になって酒樽に落ちてしまうそうですよ。
なので杜氏の方は少し斜め横から酒樽を覗くのだと教えてもらいました。
発酵途中の日本酒が無茶苦茶美味いんです。
でも、腹の中でも発酵しちゃうそうなので凄く悪酔いします(笑)
東薫ですね。
千葉では有名な造り酒屋ですな。
でも 叶というお酒は初めてです。
どぶろくは好きですよ。
私に合っているような。
あっ
日本酒も好きだったんですね。今度ゆっくりと。
あさとさん
以前に銚子の醤油工場を見学した際に聞いた話ですが、
麹菌の育成には適度に風が吹いているという要素も大事だそうです。
佐原も銚子も利根川と言う広大な川に面していますので
適度に風が吹いて醸造業には向いた土地と言う事のようです。
出来立てのお酒はやはりおいしいですよ
関西には伏見や灘と言った酒の名産地がありますので是非
試してみてください
餌釣師さん
今回、訪問した東薫酒造さんでも、酸欠で酒樽に落ちてしまう話は
伺いました。そのためこちらでは酒樽の上に床を張って、床の上から
醪を撹拌する構造にしているとの事でした。
発酵途中の日本酒は飲んだ事がないですが、
やはりおいしいのでしょうね。
いはちさん
千葉県内にもいくつか造り酒屋がありますが、こちらは県内を代表する
ところですね。本文には書きませんでしたが、こちらの杜氏は
全国杜氏協会の会長だそうです。
どぶろくは本当においしかったですよ。
実は翌週に再度、このどぶろくを買いに行ってしまったほどです(笑)